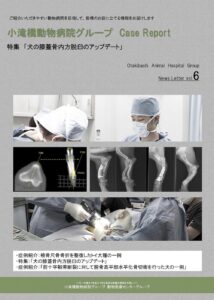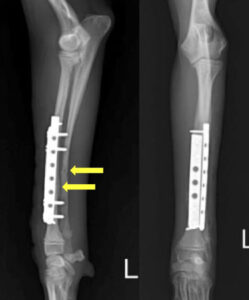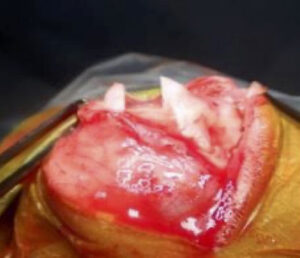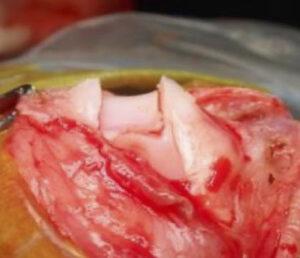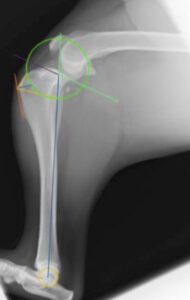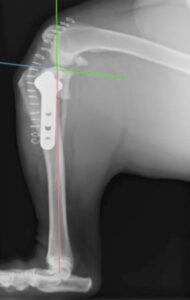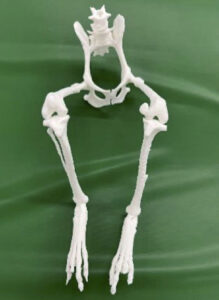MENU
-
-

PURPOSE 想いを知る
PURPOSE 想いを知る - 目指す姿 グループ代表メッセージ グループ長メッセージ
-
-
-

WORK STYLE 働き方を知る
WORK STYLE 働き方を知る - 教育体制 キャリアプラン 専科チーム紹介 獣医師インタビュー
-
-
-

RECRUIT 採用情報を知る
RECRUIT 採用情報を知る - 募集要項 福利厚生 獣医師体験型実習 よくある質問
-
-
-

COMPANY 会社を知る
COMPANY 会社を知る -
数字で見る
ミッド東京ホールディングス グループ拠点一覧
-